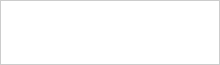「 揺らぎの中で生きる 」詩篇46:2~4
「神はわたしたちの避けどころ、私たちの砦(とりで)。苦難のとき 必ずそこにいまして、助けてくださる。」2節
年初に決心したこともどうにか守れていればよいのですが、緊張が解けてもと通りになってしまっている、この頃です。
先日の6日の朝日の社説は「先行きの見えぬ世界~わからない状態に耐える力」というタイトルでした。今の世界に住む者が必要としていることを言い当てていると思います。
ネガティブケイパビリティ(答えの出ない事態に耐える力)は精神科医 帚木蓬生(ははぎほうせい)さんの著書からのことばです。実はこのことばは19世紀のジョン・キーツが創造的な芸術家に求められる資質として語ったところから知られるようになりました。
もう一つ、紹介したい本があります。「隣の国の人びとと出会う」斎藤真理子(ハン・ガンの名翻訳者)による本です。
ある方にこの本を差し上げましたら以下のように感想を送ってくださいました。
「昨日いただいたご本。興味深く読み始めています。 ゆれる言葉と言葉の間に橋をかける…翻訳の仕事はスピリチュアルケアに似てるかも知れませんね。
異なる文化や歴史の中で培われた言葉。それを使うそれぞれの人も異なる生育歴や環境、文化、価値観を持っている。そんな人と人、自分と他者の常に揺れる間に橋をかける…なんだかスピリチュアルな感じがしてきました。
ハングルと点字も似てるなと思います。言葉をなるべく正確に伝え共有できるようにするために。異文化の間で揺れながら、また他者と自分の間でも揺れながら、人と人、言葉と言葉に橋をかける…(中略)興味深いご本をありがとうございました」
新年だから古き昨年までのことは解決済みで、まっさらな気持ちで居られる、という人はそんなに居ないと思います。 揺らいでいる気持ちでいることを嘆くのではなく、そのような自分を認めて、イエス・キリストによって伝えられた、無条件の愛の神に「苦難のとき 必ずそこにいまして、助けてくださる。」との確信を新たにして、また一歩前に進むものでありたいです。