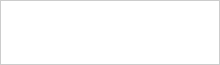「 試練を耐え忍ぶ 」 ヤコブ1:12~18
「試練を耐え忍ぶ人は幸いです。」12節
レント(受難節)に入りました。十字架にかけられる前のことです。 イエス・キリストの生涯は不条理でした。この苦しみに直面するのがクリスチャンのもう一つのアイデンティティでもあるのです。
ヤコブ書はとても実践的な内容が多く、信仰者の日常生活に役立つ教えが詰まっています。ルターは藁(わら)の書として軽蔑的な言葉を言いましたが、この書を聖書から無くせとはいいませんでした。
先月末、驚いたことがありました。
新聞の投稿欄に17歳の女子高校生が「押しが『反日』で悲しい人へ」
(朝日2025-2-28)という文章を投稿。それを読んで、34年前に同じく高校生の朝日新聞への投稿文、学校の姿勢を批判した「生きる」に驚いたことを思い出しました。学校でのキリスト教の教えに影響を受けながら、広く社会に向かって言いにくいことでもしっかりと主張し堂々と発表している姿は力強くも清々しいことでした。
どちらもキリスト教主義学校。前者はそこに努めている朴洪奎(パクホンギュ)さんからの知らせで、島根県の愛真高校の生徒と知りました。後者は私が長く務めた大阪府の清教学園高校。 クリスマスとイースター(復活節)は世に知られていますがレントは一般的にはあまり知られていません。 けれどもキリスト教の大切なできごとであり、復活節の前にこのレントがあるのです。
私は二人の高校生から、自分たちは意識していなくとも、このレントの厳しさを自分のものにしていて、今を生きる意味を表現しているように思えます。
endure(耐え忍ぶ、忍耐)」の語源はラテン語に由来します。ラテン語の「end?r?re」から派生しており、「in-」(中に)と「d?r?re」(堅くする、耐える)を組み合わせたものです。この語源が示すように、「内面で堅く保つ」や「耐え続ける」というニュアンスが含まれています。
尹東柱(ユントンジュ)の《十字架》という詩に「苦しんだ男、 幸福なイエス・キリスト」と表現しているくだりがあります。
この時期にこそ苦しみは恵であることに思いを馳せたいものです。